誰もが納得される相続内容を提案いたします
事業承継では経営者の財産を動かすため様々なトラブルが発生しがちです。
ここではトラブルを防ぎ、スムーズな相続を行うための対策方法をご紹介します。
遺言書作成

事業承継には様々な方法がありますが、そのうちのひとつが遺言によるもの。先代経営者が生前にあらかじめ遺言を作成しておくことで、死亡時に自社株などを円滑に後継者へと引き継げます。
遺言書のメリット
遺産分割協議の回避
相続が発生した時に、相続人全員で遺産の分割について協議し合意することを遺産分割協議と言います。
遺言書がなかったばかりに父親が亡くなったとたん家族が大揉め……という光景はテレビドラマなどで見たことがあるかもしれません。遺言を作成することで相続を行えば、禍根を残すことなく事業承継を終えることができます。
自社株が分散するリスクを回避
後継者をきちんと定めていても、遺言書が無いため遺産分割協議が行われて自社株が分散してしまう恐れがあります。後継者が今後の経営を安定して進めるためにも、自社株を一定以上保有することで議決権は確保しておきたいはずです。遺言によって相続させる、又は遺贈する親族を指定しておけば、事業と関係ない親族が大きな株数を持つことも防げます。
遺言書作成時のポイント

資産の整理
経営者が不動産を所有している場合は、その不動産を銀行から事業資金の借り入れの担保に提供しているケースがあります。個人が所有している不動産を会社に提供している場合には、会社と個人の契約関係を整理する必要があります。
経営者自身が会社に貸し付けている金銭も財産として相続の対象となり、相続税の対象になりますので長期的に消滅させる方向で検討しましょう。
また、経営者自身が会社が受けている融資の保証人なっていることがありますが、その債務は法定相続分に応じて各相続人に引き継がれます。
事業承継の計画は遺言書作成と並行する
後継者への事業承継を相続のみで行うと、遺留分がネックになったり相続税の納税が困難になったりすることも少なくありません。そこで、経営者が現役のうちに
- 生前贈与により株式を後継者に移譲する
- 生命保険契約により相続税の納税資金を確保する
など、事業承継に向けた計画を策定し実行することも有効です。これらの事業承継計画を実行することにより、遺言の選択肢が増えることになります。たとえば、後継者以外の親族には議決権のない株式を相続させて事業の継続に支障のないかたちで遺留分をケアすることなどが考えられます。
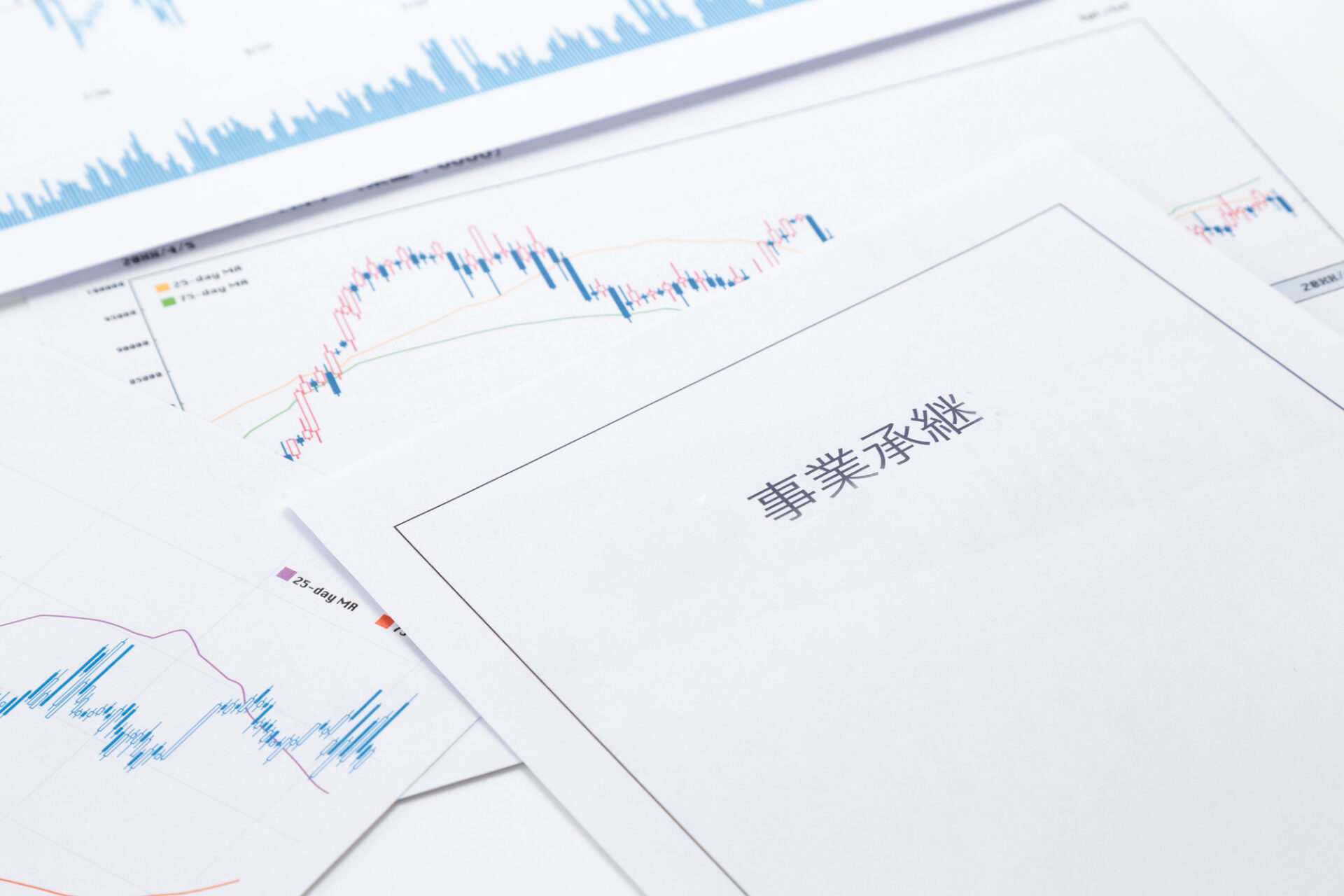
遺言書作成の流れ
STEP1 :相続人と相続割合、遺留分割合を把握する
STEP2 : 自分の財産全体の調査・評価を行い財産リストを作る
STEP3 : 今後のことも考慮し相続人の貢献度・依存度をチェックする
STEP4 : 誰に何をあげるのか財産の承継・処分方法を決める
STEP5 : 財産承継以外の遺言内容を決める
STEP6 : どの種類の遺言にするのか決める
民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)とは
信託とは「財産管理」と「財産承継」のための制度です。このうち民事信託と経営者の判断能力が低下し、自分で自己の財産を管理や処分することができなくなる備えとして、その子が親のために財産を管理するという制度です。
民事信託(家族信託)のメリット
判断能力低下後も財産管理ができる
経営者である父は、金銭と不動産等を信託財産として受託者受託者である子息へ信託します。財産の名義は子息になり、信託後は子息「だけ」が信託財産の管理や処分をすることになります。これにより父の存命中は、父は財産の管理の負担がなくなります。なぜなら父の名義の財産ではなくなるからです。他方、信託財産からの利益は引き続き父が受けることに変わりはありません。
3世代後まで承継先を決められる
遺言書の場合、指定できるのは自分が死んだ際の相続についてのみで、その先について指定することはできません。しかし、民事信託を行えば3世代先の承継先まで指定することが可能です。、受託者である子息が死亡したあとに信託財産を誰に承継させるのかまで指定することができます。このような意味で、民事信託は遺言の代わりにもなると言えます。
民事信託を考える際のポイント

元気な時にはじめておく
家族信託契約を結べる最終の導入タイミングは体調や意識の変化が現れた時です。家族信託は「信頼できる家族に財産を託し、自分や家族のために管理してもらう」制度です。しかし、実際に認知症になってからでは、家族信託契約を結ぶことはできません。
そのため、家族信託を契約する理想のタイミングは「元気な時」です。早く家族信託を結んでしまったら、後々気持ちが変わるかもしれないと不安に思われる方もいるかもしれませんが、そのような場合は、家族信託契約の内容を変更することも可能です。 万が一、認知症になってしまうと、銀行に預けている預金も引き出すことができなくなるなど、予定していた相続対策はストップしてしまうので注意が必要です。
民事信託(家族信託)の流れ
STEP1 : 家族信託の内容を話し合い、合意を得る
STEP2 : 話しあって決めた内容を契約書に盛り込み作成する
STEP3 : 財産の名義を親から子へ移す
STEP4 : 財産管理のための専用口座を設ける
任意後見契約

任意後見契約とは
任意後見契約とは、委任契約の一種で、経営者本人が、受任者に対し、将来判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を、任意後見人にすることができます。身内の者でも、友人でも全然問題ありません。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者など)は除外されます。
任意後見契約のメリット
制度設計の自由度が高い
本人の希望に沿って制度を設計しやすいということが任意後見制度の最大のメリットです。任意後見制度では、前もって本人が信頼できる人を後見人に選べます。親族はもちろん、信頼できる第三者も選任可能かつ契約内容も自由に決められます。契約内容が登記されるので、任意後見人に選ばれた人の地位が公的に証明されます。役所や銀行で手続きを行うとき、任意後見人であれば手続きがスムーズに進みやすくなるということもメリットの1つです。
任意後見契約を考える際のポイント
任意後見人は信頼できる人を選んでおく
毎月、後見監督人に支払う費用がかかる
まとめ
相続対策は非常に長い時間を要します。また、相続対策を行う争続対策、相続税対策など多岐にわたる対策が必要で1つが欠けても相続トラブルに発展してしまうことがあります。個々の事情に応じた最適な相続対策を行うためにも、まずは私どもにご相談ください。
電話でのお問い合わせ
06-7897-0971
営業時間/9:00~19:00(応相談)
定休日/土曜・日曜・祝日(対応可)